これも随分昔、PSO(ファンタシースターオンライン)というオンラインゲームでネカマしていたあの日あの時。
オンラインゲームに少しずつ慣れてきた頃の話だ。
私にはとても仲のいい女の子のフレンドがいた。
彼女は、オンラインゲーム歴が浅く、その当時まだ初心者を脱していない私よりも、さらに上をいく初心者だった。
その為、私がオンラインゲームの先輩にあたり、最近得た浅い知識を教えてあげたり、手伝ってあげたりすることが多く、私をお姉さんのように慕ってくれていた。
私自身、リアルでまったく交流のない知らない人と掛け合いをし、仲良くなっていく不思議な感覚に喜びを感じていた。
いよいよオンラインゲームの”オンライン”というファンタジーな世界の楽しさがわかってきていた。
当時のPSOというゲームについて少し話をする。
PSOには、今や当たり前となっている”ギルド”という概念がなく、仲良しが集まるコミュニティといったものは一切なかった。
そのため、野良部屋がほとんどの割合を占め、みんながみんな一期一会を楽しんでいた。
知らない人同士で「はじめまして」から始まるその後の冒険には、新鮮さとワクワクがいっぱいだった。
ほとんどの人がオンラインゲームは初めてだったし、みんなぎこちないチャットで盛り上がり、ささいな冒険に一喜一憂していた。
中に人がいて、そのキャラを動かして、すべてアドリブで掛け合いをする。そんな当たり前のことが、あの頃は感動だった。
あの頃は本当にみんな純粋で、語尾が「にゃ」の人なんて普通にいたし、キャラになりきっている人や、攻撃する時に自分で考えたであろうオリジナルの掛け声や、必殺技を叫んだりするのも普通だった。
だから私のその当時の口癖が「にはは☆」だったのも全然普通だった。
それでも誰一人として、「あいつイタイな」なんて思わなかったし、みんながみんなオンラインゲームにのめり込み、そして浮かれていたんだと思う。
みんなが浮かれていて、それでいて純粋で、カオスでこれぞ”ネットの世界”という感じだった。
思い出補正はあるだろうが、本当にどこにいっても、何をしていても新鮮で面白かった。
今はもう絶対に再現出来ない最高の遊び場だったと思う。
そんな初心者時代を一緒に過ごしただけあって、私と彼女はどんどん仲良くなっていった。
彼女から見た私は、頼れるお姉さんであり、コミュニティの一切なかったあの当時の唯一のフレンドでもあった。
そして、言いたいことをガンガン言って、グイグイ引っ張るスタイルや、リアルで夜出かけることが多かった私を見て、なぜか彼女は私を不良だと認識していった。
彼女の中では[夜に出歩く=不良]と解釈されていたようで、そしてそれは[不良=経験豊富なビッチ]にも繋がっていた。
つまり、私は知らぬ間に、経験豊富でビッチな頼れるヤンキーお姉さんという人物像になっていたのだ。
そうなるとどうなるか。
そう、めちゃくちゃ恋愛相談されるようになっていったのだ。
彼女には、付き合って間もない彼氏が存在し、その愛する彼氏にどうすればもっと好きになってもらえるのか、どうすれば彼は喜ぶのか、というとても純粋で可愛らしい質問を私にしてくるのだ。
いや、リアルの友達にしろよとも思ったが、経験豊富でビッチな先輩ならきっといい方法を知っているだろうという熱い眼差しがその質問からはっきりと感じ取れた。
しかし、私は歳もほぼ彼女と変わらない上に、経験豊富なビッチでもなければ、ましてや女ですらない。
明らかに質問する相手を間違っていたのだが、そんなことは彼女は知るよしもなかった。
だが、私は彼女からの質問に的確にアドバイスをしてあげることができた。
なぜなら、私は男だ。彼氏がどうしてほしいか、どうすれば喜ぶかではなく、男である自分ならどうしてほしいか、どうすれば喜ぶかを答えるだけで良かったのだ。
彼女が話す彼氏とのエピソードを聞きながら、その彼氏に自己投影し、その時どうしてほしかったのか、どう思っていたのか、自分の意見を述べるだけだった。
男心がわからない彼女からすると、”なるほど~”と納得しきりのようで、「さすがだね!」と言って毎回感心していた。
だが、なにもさすがではなかった。1ミリも彼氏の心情など考えておらず、ただただ自分ならこうかなという話をしただけだった。
それでも彼女は、男心が手に取るようにわかる私を絶賛し、尊敬の念を込めて「モテるだろうな~」と言うのだった。
そんな日々が続き、彼女から得られる信頼は日に日に大きくなり、頼れる先輩度はグングンと上昇していた。
そして、ついに彼女はこんな相談を私にする日が来てしまった。
彼氏と”初体験”をしたという話だった。その初体験の内容に関する相談だったのだ。
内容はそれはもう、ビックリするくらいの下ネタで、今までのほんわかラブストーリーとは訳が違っていた。
いきなり彼女はアクセルペダルを全力で踏み込み、全速力で私めがけて突っ込んできたのだ。
これまでの私のアドバイスが功を奏したのかはわからないが、ほのぼのしていた絵本のような内容から、急に人体の不思議についての内容になった。
全速力で迫られすぎて、かわしようがなく、非常に困ってしまった。なぜなら、私はなにを隠そうその当時まだ童貞だったのだ。
もうちょっと段階があるだろ・・・と純粋に思った。ある程度のステップを踏んでくれていれば、こちらも心の準備はできたはずだった。
彼女が答えを求めようとしているのは、経験豊富でモテモテな頼れるお姉さんだった。しかし、実際に答えを求めたのは、テンパった童貞だった。
とてもじゃないが、実践経験のない童貞の私が答えられるような内容ではなかった。内容は下ネタすぎてここに書くことはできない。
しかも、ここに来て、女でないとわからない内容だったのだ。ここに来てだ。女の人体の不思議を私に求められても、わかるはずがなかった。
だが、ここまで来て彼女の尊敬する頼れるお姉さんがあたふたする訳にはいかなかった。
私がそのとき得ている信頼と、イメージを崩すわけにはいかない。そう思った。なんとかするしかなかった。
そんな焦りと同時に、男である私が聞いてはいけない話を聞いてしまっている現状に、ひどい背徳感を覚えていた。
同級生くらいの純粋な女の子があられもない言葉を発するのだ。はっきり言おう。興奮しないわけがない。
その時感じた”非日常感”は今でも鮮明に覚えている。自分の体がフワフワ浮いている。そんな感覚だった。
客観的に見て、死ぬほど気持ち悪い上に、彼女のことを考えると最低なクソヤロウだと今になって思う。
その時に、ない知識をかき集めてしたアドバイスも、今思いだすと目を覆いながら懺悔するレベルのものだった。
もちろん、そんなこと彼女は知らない。
私が必死に絞り出した童貞の妄想である答えも、純粋に頼れるお姉さんからの言葉として受け取っていた。
そして彼女はいつものように「さすがだね!」と言うのだ。
そんな彼女との関係も、半年ほど続いたところでだんだんと疎遠になっていった。
お互いオンラインの世界で色んなフレンドができたり、私が違うゲームモードで遊び始めたりと、無限の可能性が広がった世界をお互いが歩み始めたのだ。
それでもたまに連絡をくれて、呼び出されたところで仲良くなったフレンドを紹介してくれて、私のことを”師匠”なんていう言い方をして紹介してくれる。
そこには、半年前の”ド素人”だった彼女の姿はなく、立派に色んなフレンドを作ってオンラインゲームを楽しんでいる彼女の姿があった。
そして彼女が色んな冒険の話をしてくれるのを聞きながら、私は「にはは☆」と笑うのだった。
当時の記憶が蘇ると、あの時代に帰りたくなる衝動にかられる。
誰でもあると思うが、初めてのオンラインゲームは思い出補正もあってか楽しさのレベルが桁違いだった気がする。
自分が純粋だった頃、新鮮さとワクワクがあふれている世界はあんなにも輝いていた。ファンタジーの世界だった。
それがいつのまにか、ファンタジーだけでは満足出来なくなってしまっていた。
心にあった純粋さは汚れてなくなり、からっぽになった心を、地位や名声などいらないものばかりを求めて、埋め合わせをしているのだ。
だから、ファンタジーの世界はどんどん醜くなっていく。だから、こんなにも昔を懐かしむのだ。
彼女とはPSOがサービス終了する際にお別れをし、「師匠、元気でね!」というグッとくる言葉をもらってサヨナラした。
今でも彼女の思い出には、きっと頼れるビッチな先輩は生き続けているんだと思う。
あの時代に、あんなに純粋に楽しめたのは彼女のおかげかもしれない。今になってそう思う。
彼女と過ごしたファンタジーな日々の思い出は、今でも私の宝物だ。












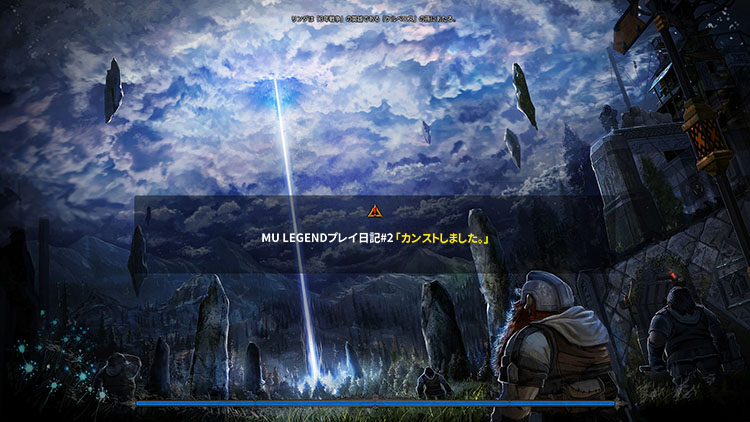



文章力がすごく高いですね・・。
最後までじっくり読んでしまいました。面白い。
やったぜ褒められた!
ブログの励みになります。ありがとう!
いい話だなぁ〜
しかし、その娘も実はネカマであったのである。終
感動した
心が洗われた気がするよ。やっぱり所詮はゲームでも、立派な思い出なんだなって改めて思った。
泣きたくなるほど切なくなってきたが、この気持ちを忘れないようにするよ。
ちょびっと泣きそうです。ほかの方も言っていますが、文章力が高いので笑うところもありました。自分も初めてプレイしたオンラインゲームはドキドキが止まりませんでした。今ではそんなこともなくイライラしながらゲームをすることが多いです。忘れていた気持ちを思い出させてくれました。ありがとう。
やってるのはゲームだが、それを通じてプレイしてるのは人間だからな。そこを忘れがちな今の若いやつに活!
人気で人集めやすいオンゲは面白いですね。老若男女いろいろな人がいて楽しい。
笑った